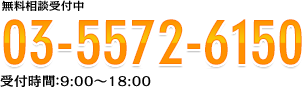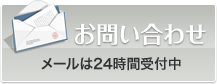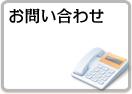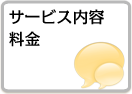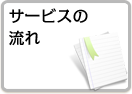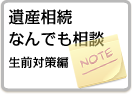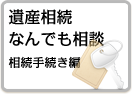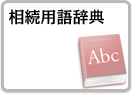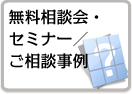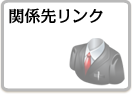わかりづらい相続用語を解説いたします
あ行
|
いごん・ゆいごん |
人の死後において、その人の意思を実現する為の法律行為を遺言といいます。法律上その内容として、認知、相続人の廃除とその取消し、相続分の指定、遺産分割方法の指定または禁止、遺贈などが認められています。 遺言は「ゆいごん」とも読まれますが、法律用語としては、「いごん」と読まれます。 |
|---|---|
|
いごんしっこうしゃ |
遺言の内容を実現するために選任される者のことを遺言執行者といいます。遺言執行者は、遺言の執行に必要な一切の行為を行い、相続人も遺言の執行を妨げる行為をすることはできません。 |
|
いごんしょうしょ |
法定の方式によって遺言を記載した書面のことを遺言証書といいます。代表的な遺言の方式に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。 |
|
いさんぶんかつ |
相続人が複数いる場合、被相続人の死亡と同時に、相続財産は相続人全員の共有となります。このような状態から、具体的に相続財産を分配する行為を遺産分割といいます。 |
|
いさんぶんかつきょうぎ |
遺産分割の方法を共同相続人で定める協議のことを遺産分割協議といいます。そして、協議で合意した分割方法を書面にしたものを遺産分割協議書といいます。 |
|
いぞう |
被相続人が遺言により、相続人または相続人以外の第三者に財産の全部または一部を取得させることを遺贈といいます。 |
|
いりゅうぶん |
一定の相続人のために、法律上必ず残しておかなければならない遺産の割合を遺留分といいます。なお、遺留分の割合は、一部の例外を除いて、各法定相続人の法定相続分の2分の1となります。 |
|
いりゅうぶん げんさいせいきゅうけん |
遺贈や死因贈与などが遺留分を侵害する場合に、遺留分の限度まで、遺贈や死因贈与を取り戻す請求を遺留分減殺請求権といいます。 |
|
いりゅうぶんのほうき |
相続人が、自らの遺留分への侵害を認めることを遺留分の放棄といいます。法定の遺留分の割合より少ない持ち分で納得することであり、相続全部を放棄する相続放棄とは異なります。 |
|
えんのう |
相続税を申告期限までに全額納付できないような場合に、一定の要件のもと、相続税を分割払いすることを延納といいます。 |
か行
|
かんかぶんかつ |
相続で取得した財産の全部または一部を処分した上で各相続人がその代金を分割する方法を換価分割といいます。 |
|---|---|
|
きそこうじょがく |
相続税が課税されない財産額の範囲のことを基礎控除額といいます。 |
|
きょうぎぶんかつ |
共同相続人の協議によって、遺産分割をすることを協議分割といいます。 |
|
きよぶん |
共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加に特別に寄与した者に対して与える法定相続分以外の特別の取り分を寄与分といいます。寄与分がある場合は、財産の価格からその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、その者の相続財産に加えます。 |
|
げんていしょうにん |
被相続人から承継する相続財産の限度で、相続債務または遺贈を弁済する相続の方法を限定承認といいます。注意点としては、相続開始を知った日から3か月以内に申述することと、相続人が複数いる場合は、全員の合意が必要となります。 |
|
けんにん |
家庭裁判所で遺言執行前の遺言書の形式や内容等を確認し、偽造・変造を防ぐ手続きのことを検認といいます。封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人等の立会いの上、開封しければなりません。この検認を怠ると5万円以下の過料が科されます。なお、公正証書遺言書では検認は必要ありません。 |
|
げんぶつぶんかつ |
遺産をそのまま分割する方法で、土地と家屋は配偶者に、現金は長男になどと個々の財産を現物のまま分割する方法を現物分割といいます。 |
|
こうせいしょうしょいごん |
法律に定められた手続きによって、公証人が作成する遺言方式のことを公正証書遺言といいます。証人2人以上の立ち会いが必要であり、原本が公正人役場に保管されます。 |
|
こうせいのせいきゅう |
申告をした税額が過大であることがわかった場合に、納税者が申告税額の訂正を請求することを更正の請求といいます。 |
さ行
|
ざいさんもくろく |
相続財産のプラスやマイナスなどを調べ、遺産の範囲及び財産状態を示すために作成する目録のことを財産目録といいます。 |
|---|---|
|
さいむこうじょ |
被相続人の債務として相続開始の時に確定しているものや、通夜・葬式・火葬・納骨等の葬式費用を課税財産から差引くことを債務控除といいます。 |
|
しいんぞうよ |
贈与者の死亡によって効力が生ずる贈与契約のことを死因贈与といいます。 |
|
じぎょうしょうけい |
会社の経営を現在の経営者から後継者に引継ぐことを事業承継といいます。 |
|
していそうぞくぶん |
法定相続分にかかわらず、被相続人は遺言または第三者への委託によって、相続分を定めることができます。このようにあらかじめ指定された相続分を指定相続分といいます。 |
|
していぶんかつ |
被相続人が遺言または第三者への委託によって、相続財産の分割方法を指定することを指定分割といいます。 |
|
じひつしょうしょいごん |
遺言者がその全文、日付を自書し、署名、押印をする遺言方式のことを自筆証書遺言といいます。遺言者が自分で全文を書かなければならず、ワープロなどで作られたものは無効となります。 |
|
しぼうたいしょくきん |
被相続人の死亡によって取得した退職金のことを死亡退職金といいます。被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の対象となります。 |
|
しぼうほけんきん |
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金のことを死亡保険金といいます。その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続財産とみなされて相続税の対象となります。 |
|
しゅうせいしんこく |
申告をした税額が過少であることに気がついた場合に、納税者が申告税額の修正申告書を提出することを修正申告といいます。 |
|
じゅんかくていしんこく |
被相続人が亡くなった年の1月1日~死亡した日までの、所得を申告することを準確定申告といいます。 |
|
しんぞく |
民法上では、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族のことを親族といいます。 |
|
しんぱんぶんかつ |
遺産分割協議が整わないとき、または協議をすることができないときなどに、家庭裁判所が分割の審判をすることを審判分割といいます。 |
|
すいていそうぞくにん |
民法の規定に従って相続人になり得る人のことを推定相続人といいます。実際に推定相続人の全員が相続人となるわけではありません。 |
|
せいぜんぞうよかさん |
相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算するという制度のことを生前贈与加算といいます。 |
|
そうじそうぞくこうじょ |
相次いで相続が発生した場合には、相続税を支払う人にとって負担が大きくなる為、相続税額から一定金額を差し引く制度のことを相次相続控除といいます。 |
|
そうぞく |
亡くなった人の財産上の権利や義務を、家族などの相続人が受け継ぐことを相続といいます。 |
|
そうぞくけっかく |
相続人に一定の非行がある場合に、相続人の資格を失うことを相続欠格といいます。 |
|
そうぞくざいさん |
相続によって相続人に移転する財産的な権利義務のすべてを相続財産といいます。 |
|
そうぞくざいさんのきふ |
相続や遺贈により取得した財産を国や、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄付した場合には、その寄付をした財産は相続税の計算上課税財産から除かれるという特例のことを相続財産の寄付といいます。 |
|
そうぞくざいさんほうじん |
相続人の存否が明らかでないときは、相続財産は法人とし、これを相続財産法人といいます。 |
|
そうぞくじ せいさんかぜいせいど |
生前贈与の受贈者が贈与時に贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産を合計した価格をもとにして相続税を計算する、そして相続税からすでに支払った贈与税を控除するという制度のことを相続時精算課税制度といいます。生前贈与を行いやすくし、次世代に財産を早めに移すことを目的とした制度となります。 |
|
そうぞくぜい |
相続により財産を取得した場合に、課せられる税金のことを相続税といいます。 |
|
そうぞくにんのはいじょ |
被相続人に対して、虐待したり重大な侮辱を与えたりなどの非行が相続人にあったような場合、その相続人の相続権を失わせることを相続人の廃除といいます。 |
|
そうぞくほうき |
被相続財産について、プラスもマイナスも一切引き継がないとする意思表示を相続放棄といいます。注意点としては、相続を放棄した場合は、その相続人がはじめから相続人でなかったものとみなされ、代襲相続することはできません。また相続開始を知った日から3か月以内に申述することが必要となります。 |
|
ぞうよ |
生きているうちに無償で自己の財産を与えることを贈与といいます。 |
|
ぞうよぜい |
贈与により財産を取得した場合に、課せられる税金のことを贈与税といいます。 |
|
ぞうよぜいの はいぐうしゃこうじょ |
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産またはその購入資金の贈与を受けた場合に、基礎控除110万円とは別に最高2,000万円までの控除の適用を受けることができる制度を贈与税の配偶者控除といいます。 |
た行
|
だいしゅうそうぞく |
相続人の権利がある者が、被相続人より先に死亡している場合、または相続欠格、相続人の廃除によって相続権を失った場合に、その相続人の子が親に代わって相続することを代襲相続といいます。 |
|---|---|
|
たんじゅんしょうにん |
被相続人の財産をプラスもマイナスも全て無制限に相続することを単純承認といいます。相続開始後、3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしない場合は、単純承認したものとみなされます。 |
|
だいしょうぶんかつ |
相続財産の全部または大部分を特定の相続人が相続する代わりに、その相続人が他の相続人に対し自分が所有している金銭等の別の財産で支払う方法を代償分割といいます。 |
|
ていきぞうよ |
贈与者が受贈者に対して定期的に贈与を行うことを約束した贈与契約のことを定期贈与といいます。 |
|
とくていいぞう |
相続財産のうち特定の財産を遺贈すること特定遺贈といいます。 |
|
とくべつじゅえき |
相続人が被相続人から生前に、特別の財産をもらっていた場合のことを特別受益といいます。 |
|
とくべつじゅえき のもちもどし |
特別受益を得ている相続人がいる場合は、特別受益を遺産の前渡し分と考え、相続財産にその額を加算することを特別受益の持ち戻しといいます。 |
|
とくべつえんこしゃ |
被相続人と生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者、被相続人と特別の縁故があった者などを特別縁故者といいます。特別縁故者は、相続人の不存在が確定した後、家庭裁判所に請求することで相続財産の分与を受けることが出来ます。 |
な行
|
にわりかさん |
相続や遺贈によって財産を取得した人が、その被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額の2割に相当する金額を加算することを2割加算といいます。 |
|---|
は行
|
ひそうぞくにん |
亡くなった方のことを被相続人といいます。 |
|---|---|
|
ひちゃくしゅつし |
法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことを非嫡出子といいます。非嫡出子も法定相続人となり、法定相続割合は嫡出子と同じになりました。 |
|
ひみつしょうしょ ゆいごん |
遺言書の存在は明かしつつ、内容を秘密にして偽造、隠匿等を防止する遺言方式のことを秘密証書遺言といいます。遺言書に署名・押印をした後に封印し、遺言者が公証人と証人2名の前で自己の遺言書である旨などを申述し、関係者が署名・押印をする必要があります。 |
|
ぶつのう |
相続税を延納によっても金銭で納付することが困難である場合に限って、一定の要件のもと、相続税を相続財産そのもので納めることを物納といいます。 |
|
ほうかついぞう |
相続財産の全部または一部を遺贈すること包括遺贈といいます。 |
|
ほうていそうぞくにん |
民法によって定められた相続人になれる人の範囲のことを法定相続人といいます。相続人になれる人の範囲は、被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹となります。 |
|
ほうていそうぞくぶん |
法律によって定められた相続人の相続分のことを法定相続分といいます。法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの割合であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。 |
|
ほんらいのざいさん |
民法の規定に従って相続等により取得する財産のことを本来の財産といいます。土地、家屋、借地権、株式、預貯金、現金、貴金属、宝石、書画、骨とう、自動車、電話加入権、立木、金銭債権など、金銭に見積もることが可能なものは、全て相続税の対象となります。 |
ま行
|
みせいねんしゃこうじょ |
相続や遺贈により財産を取得した者が、民法上の法定相続人に該当し、かつ20歳未満であった場合は、その者の負担すべき相続税から、6万円にその者が20歳に達するまでの年数を乗じて得た金額を控除する制度のことを未成年者控除といいます。 平成26年12月31日まで 未成年者控除額= 6万円×(20歳-相続開始時の年齢) |
|---|---|
|
みなしそうぞくざいさん |
税法上、本来は相続財産ではないが、被相続人の死亡を原因として、相続人のもとに入ってきた財産を、みなし相続財産といいます。死亡保険金、死亡退職金などがこれに当たりますが、民法上の相続財産ではないため、これらは遺産分割の対象となる財産には含まれません。 |